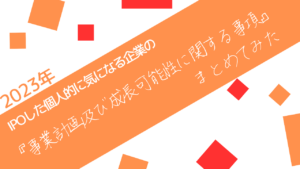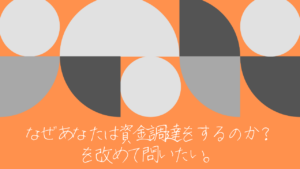ソリッドベンチャーとは、創業初期から黒字の既存事業(キャッシュエンジン)を持ち、その利益を新規事業の探索と再投資に回し続けられる“状態”にある企業のことです。赤字を前提としたJカーブ型スタートアップとは異なり、黒字基盤が倒産リスクを下げ、事業の探索を継続する余力をもたらします。さらに、外部資本の量やタイミングを自分で選べる点も大きな特徴です。実際、IPOしている企業の多くはこの「ソリッド状態」で成長しており、Jカーブで一気に跳ねる企業は世間のイメージよりはるかに少数です。
定義と前提
【定義】ソリッドベンチャーとは“状態”である
ソリッドベンチャーという言葉は私の造語ですが、その本質は新しい概念というより「昔からある強い会社の構造」を言語化したものです。創業初期から売上と利益を出し、その収益を事業成長や新規事業に回し続けることができる──この状態がソリッドベンチャーです。
この状態を維持している企業には、いくつか共通点があります。まず、創業初期から黒字化できるビジネス(受託開発、ITコンサル、代理店など)でキャッシュエンジンを作ること。次に、その利益を探索的な新規事業へ少しずつ投資し、事業の柱を増やそうとすること。そして、必要なときにだけ外部資本を使い、自社のPLやキャッシュフローを自分でコントロールできることです。
特徴をまとめると、
- 創業初期から売上が立つ事業で黒字化(=キャッシュエンジン)
- その利益を新規事業に回し、探索を継続できる構造
- 必要なときだけ外部資本を使い、タイミングを自分で決められる
つまり、ソリッドベンチャーとは「黒字 → 再投資 → 探索」のループを止めずに回せる企業の状態を指します。
【前提】IPO企業の多くはソリッド構造
スタートアップ業界では「Jカーブで一気に成長する企業」が注目されますが、IPOの実データを見ると実態は大きく異なります。
- 毎年100社前後のIPOのうち
- 創業5〜20年程度のベンチャーは約40社
- そのうち純粋なJカーブ型は4〜5社だけ
という現実があります。
年間100社ほどがIPOする中で、創業5〜20年ほどのベンチャー企業は約40社。そのうち純粋なJカーブ型で上場している企業はわずか4〜5社に過ぎません。残る多くの企業は、創業初期から売上と利益を積み上げてきたソリッド型です。
つまり、派手に跳ねるJカーブは“目立つだけで少数派”。
実際の市場では、堅実に黒字を積み重ねながら成長していく企業が主流であると解釈しています。
ソリッドベンチャーがいま注目される理由
近年、ソリッドベンチャー型の企業が再び注目される背景には、いくつかの構造的な変化があります。
高金利化と資本コストの上昇
まず、世界的に金利が上昇し、資本コストが高騰しているため、「赤字前提で資金調達を繰り返すモデル」が成立しづらくなっています。調達のたびに企業の寿命が左右されるようなJカーブ型は、キャッシュアウトのリスクが大きすぎるのです。
倒産率の上昇と起業家/社員の精神衛生の観点
さらに、倒産率が高まりつつある現在では「キャッシュが尽きた瞬間に終わる会社」が増えています。起業家にとっても社員にとっても、口座残高を睨みながら経営する状態は精神衛生上よくありません。安定収益を持つソリッド型企業は、この不安定さを避けつつ、挑戦を続けられます。
M&A市場での需要増加
加えてM&A市場でも、黒字基盤を持つ企業は買収されやすく、ソリッド型の方が圧倒的に評価されます。
こうした外部環境の変化が「堅実に稼ぎつつ大きな挑戦ができる企業構造」へ注目を集めている理由です。
キャッシュエンジンの作り方
ソリッドベンチャーの源泉は “創業初期から黒字を作る既存事業” にあります。創業初期から黒字を作ることができる「キャッシュエンジン」の確立が必須です。受託開発、ITコンサル、SES、広告代理店、代理店事業、業務請負など、すぐに売上が立つビジネスを選ぶことで、会社は早期に黒字化できます。
黒字化した後は、その利益を小さな新規事業に再投資していきます。顧客からの声や日々の業務の中にある“外しにくいニーズ”を見つけ、まずは小さく試し、伸びそうなものは拡大し、Jカーブ的な事業になり得るものを育てていく。
この「既存黒字 → 小さく投資 → 育ちそうなら拡大 → 場合によって外部資本で加速」というサイクルを自力で回せる企業こそが、ソリッドベンチャーの本質を体現しています。以下に簡単なステップをまとめておきます。
ステップ1:既存収益の確立
代表的なモデルは圧倒的な差別化が”できない”領域です。
- 受託開発
- ITコンサル
- 広告代理店
- BPO/SES
- 物販/代理店
- 業務請負
これらの差別ができない事業に共通するのは 「すぐに売上が立ち、利益を出せる」 こと。これが倒産リスクを圧倒的に下げ、挑戦の土台になります。
ステップ2:再投資のループ設計
安定収益を得たら、次は以下のループを設計します。
- 既存事業で黒字化
- その利益を小さく新規に投下
- 顧客ニーズから“外しにくい”テーマを探す
- Jカーブ的事業へ育ちそうなら投資拡大
- 外部資金は必要な時だけ選択的に入れる
この再投資ループを自力で回せることで「状態としてのソリッドベンチャー」 になっていきます。
・ソリッドベンチャーは「ラベル」ではなく 企業構造の“状態”。
・黒字基盤からの再投資で新規事業を継続探索できる。
・外部資本を“必要なときだけ使える”優位性がある。
既存収益の作り方
ソリッドベンチャーの根幹は “毎年黒字を作り続ける構造” にあります。受託から継続契約へ、コンサルからサブスクモデルへ、SESから請負へ、代理店からストック型ビジネスへ──など、既存事業を安定化させる仕組みをつくることで、新規事業へ投資する余力が生まれます。
- 受託→継続契約化
- コンサル→サブスク化
- SES→請負化
- 代理店→ストック収益化
この既存収益の積立が安定しない限り、新しい挑戦を長期で続けることはできません。
既存事業の利益再投資
実際に再投資のループを機能させるには、既存事業のKPIを徹底的にコントロールし、固定費の軽さを保ちながら運営していくことが重要です。大きく張らず、小さく試し、徐々にスケールさせる──そういう“軽やかな新規事業の探索”がソリッドベンチャーの特徴です。
また、外部資金は「PLが見え、伸ばせる確信がある段階」で初めて入れるべきだと個人的に思っています。黒字と新規探索のサイクルを繰り返すことで、企業は倒産のリスクを抑えながら成長できるようになります。
・既存事業のKPIを完全にコントロールする
・固定費をコントロールできる“軽さ”を維持
・大きく張らず小さくテスト→徐々に拡張
・外部資金はPLが見える段階で入れる
・「黒字 × 新規探索」を絶えず続ける
Jカーブビジネスへの個人的な見解(ネガティブ)
個人的には、Jカーブのビジネスモデルを構築するというようなビジネスモデルは、正直ネガティブで懐疑的です。
会社はその法人自体が存続をしつづけなければ意味がありません。なくなってしまえば、その言葉の通り、会社の法人格も、株も、代表を務めていた取締役の仕事も、何もなくなってしまいます。
先述の通り、Jカーブのビジネスモデルは創業初期から赤字を作り出し、どこかのタイミングで大きく浮上。指数関数的な成長ののちにIPOまたは大型M&AでExitがストーリーになっています。
Jカーブで大きく浮上するというのがポイントで、実は創業者も投資家も、いつ・どのタイミングで浮上するかというのがわかりません。早ければ早期に浮上する”かもしれない”しれません。
ただ、多くのJカーブビジネスのスタートアップは、Jカーブで思うように浮上できず、売上の立っている事業もなく、会社が存続できなくなってしまう手前で、新たな資金調達をする‥‥。延命措置的な資金調達を繰り返したあと、残念な結果になってしまう‥‥。
起業家はJカーブでビジネスを浮上させようともがきながらも、銀行の残金を気にして常に資金繰りとファイナンスを考えるのは精神衛生上よくないはずで、投資家としても、Jカーブがいつ浮上するかわからない中での0か100かの博打的投資になってしまいます。
これは、私の性格上怖くて起業家の立場にも、投資家の立場にもなれません。それは、売上と利益を大切にするソリッドベンチャー的な状態が長い事業会社にいたからかもしれません。
新規事業の責任者として、毎日売上のモニタリングをしながら、P/Lを更新し、販促・マーケ予算を策定。メンバーのキャリアを考えながら、人件費・固定費をも考える。
できる限り経営における指標をコントロールできる状態にしておくことが大切だと骨の髄までしみ込んでしまっています‥‥。
その点、ソリッドベンチャーは自分でPLやキャッシュフローをコントロールしながら新規事業に挑戦できます。会社が“死なない”という前提があることで、挑戦は持続的になり、メンバーの心理的安全性も確保されると信じています。
一般的なスタートアップとの違い
ソリッドベンチャーを理解するうえで、一般的にイメージされるスタートアップとの違いを整理しておくことは重要です。どちらも「新しい事業を生み、大きな成長を目指す」という目的は共通していますが、前提としている経営思想やリスク設計は大きく異なります。
一般的なスタートアップは、新規市場×新規プロダクトという“ド新規”の領域に挑戦するケースが多く、創業初期から赤字が続きます。プロダクト開発やマーケティングに先行して投資し、外部資本を入れながら短期間で一気に市場を取りに行く──こうした「Jカーブ型」の成長モデルが前提です。成功すれば大きなリターンが期待できる一方、プロダクトが立ち上がる前に資金が尽きてしまうケースも多く、調達環境や景気の影響を強く受けやすい構造になっています。
一方でソリッドベンチャーは、創業初期から黒字の既存事業を持ち、その収益を土台に新規事業へ挑戦するというアプローチを取ります。先に地に足のついた収益基盤があるため、会社の“生命線”が安定しており、新規事業がうまくいかなくても会社が即座に倒れることはありません。探索のスピードはスタートアップほど速くないかもしれませんが、外さない確度が高く、持続的に挑戦できるのが特徴です。
つまり、一般的なスタートアップが「短期で大きな跳ねを狙うモデル」だとすれば、ソリッドベンチャーは「黒字基盤を保ちながら長期で挑戦し続けるモデル」です。どちらが優れているかではなく、“会社が取れるリスク構造”によって選ぶべきアプローチが変わります。原資が限られる創業1〜3年の個人起業・小規模ベンチャーではソリッド型の方が再現性が高く、逆に大規模市場の覇権を狙うハイリスク・ハイリターンの戦いではスタートアップ型が向いている場合もあります。
1. 成長モデルの違い
スタートアップ: Jカーブ前提。短期で一気に跳ねさせる“ブリッツスケール”型。
ソリッドベンチャー: 既存基盤を使い、段階的に積み上げる“低リスク・中速成長”型。
2. リスク設計の違い
スタートアップ: 赤字前提。資金が尽きれば終了リスクが高い。
ソリッドベンチャー: 黒字基盤あり。新規が外れても会社が死なない。
3. 資本政策の違い
スタートアップ: 連続的な資金調達が必須。外部資本依存度が高い。
ソリッドベンチャー: 自走しながら必要時のみ外部資本を入れる選択式。
4. 挑戦の持続性の違い
スタートアップ: 短期集中で一発勝負の側面が強い。
ソリッドベンチャー: 黒字を維持しながら何度も挑戦できる「継続可能な探索」。
ソリッドベンチャー事例:INTLOOP、ボードルア、ユナイトアンドグロウ、ミギナナメウエ、C-mind
ここでは、いわゆる「Jカーブビジネス」ではなく、堅実に売上を重ねた上で新たな事業にも挑戦している5社を挙げます。どれも、スタートアップのように急拡大を目指す選択肢もありえますが、まずは“手堅い事業”をベースにし、社内新規をジワジワ拡大させている点がソリッドベンチャー的といえるでしょう。上場有無に関係なく、いずれも初期からとにかく赤字拡大をするスタイルではない点が共通しています。
INTLOOP
- 概要
2022年にIPO。設立2005年。ITコンサル〜フリーランス人材を組み合わせたコンサルティング事業が主軸。2024年7月期で年商270億円を超えるなど、綺麗に伸ばしています。 - 創業の流れ
製造業×ITコンサルという形で創業し、創業期からクライアントワーク中心に売上を積み上げる。そのうえでクライアントの要望に沿って、フリーランス人材を使ったプロジェクト組成を独自のビジネスモデルに拡張。 - ソリッドポイント
いきなりVC資金で赤字を掘るわけではなく、稼働人員を増やすほど売上が伸びる仕組みを着実に拡大してきた。さらに、IT人材不足というニーズを確信してフリーランス人材プラットフォーム化を行うことで、新規の柱を追加している。「受注してから着実に人員配置でPLコントロール」を徹底し、会社がコケにくいのが特長です。
ボードルア
- 概要
2021年に東証グロース市場へ上場。時価総額1,000億円突破も。ITインフラ領域のコンサル・設計・運用といったSES・請負事業で堅実に成長。 - 創業の流れ
創業期はSES事業をベースに、エンジニアの質の高さをアピールして堅調に売上を積み上げる。そこから自社のR&D組織を立ち上げ、クラウド・セキュリティ領域の新技術を吸収し、より上流コンサルやストック型ビジネスを拡張していった。 - ソリッドポイント
外部資本をほぼ入れずにIPOするという、ソリッドベンチャー的な象徴例。キャッシュが潤沢な分、急拡大しそうな事業があれば投資する準備は整っているし、赤字転落リスクは極めて小さい。ITインフラという“巨大かつ既存の市場”でしっかり受注拡大→上流に乗り出すという堅いセオリーを地で行っています
ユナイトアンドグロウ
- 概要
2019年にIPO。創業以来ずっと黒字経営のまま、従業員数が増え続けている。中堅・中小企業に特化した「情シス部門支援」のシェア型コンサルが主軸。 - 創業の流れ
「社内の情シス部門をまるっと手伝ってほしい」「でもそこまで大きいコストはかけられない」というニッチで深刻な顧客課題を捉えて、月額会員制型の支援サービスを開始。以後は顧客が安定継続し、売上が右肩上がりに。 - ソリッドポイント
既存事業である情シス支援は、労働集約型に見えつつも、会員制モデルでストック収益を積み上げる形になっている。ベースが安定すると、追加で人材紹介やITコンサルなど「ジワ新規」を起こせる。それを本当にやってきた結果、規模拡大&上場に成功しました。
ミギナナメウエ
- 概要
2018年設立、売上高が20億円規模を超えている若い会社。採用コンサルや転職エージェント事業、SES事業を持ち、創業から複数のサービスを併走しながら黒字成長を続けている。 - 創業の流れ
創業者が採用分野の知見を持っていたため、コンサル&エージェントという堅実モデルで創業。顧客から派生したニーズでSES(技術者の常駐支援)にも展開し、さらに新規事業を追加。人×売上のビジネスではあるが、クライアントを固定化しやすく、撤退リスクも低い。 - ソリッドポイント
新規事業を始めるたびに、既存顧客のニーズを調べ、「コケにくいか」を検証してから動いている。売上の上積みペースはとても早いが、“巨額の赤字”を抱えることはしていないので、仮にどこか1つが外れても倒産リスクは小さい。まさにソリッドベンチャー。
C-mind
- 概要
2011年設立。2023年2月期の売上高35億円。創業時から通信領域の代理店事業で堅調に伸ばし、そこからBtoC商材での新規を増やすなど、15期連続で売上増収。 - 創業の流れ
まずは通信の代理店事業(スマートフォン販売・ネット回線など)から入り、安定的なキャッシュフローを確保。そこから「固定費が少なく、撤退もしやすい」商材を選びつつ、新しいサービス展開に投資。結果として定額プリンターやリクルートスーツ無料レンタルなど、ユニークな新規事業を起こせています。 - ソリッドポイント
通信分野は過当競争に見えますが、それでも「代理店モデル」は仕組み次第で十分な利益が出せる。そこで出来た利益を「ジワ新規」に注ぎ込むわけです。新規事業がもしうまくいかなくても、コアの代理店事業で倒産回避というのがソリッドベンチャー的な強さ。
ソリッドベンチャーの魅力と今後
こうしたソリッドベンチャーの存在は、「スタートアップ=赤字拡大が当たり前」という常識を覆すものだと言えます。大きくまとめると以下が魅力です。
- 着実な売上と黒字経営初期から受託、コンサル、代理店など確実に稼げるモデルでスタート。倒産リスクが低く、従業員や顧客も安心。
- ジワ新規でコケにくい既存事業のお客さんからニーズを拾って新サービスを作る → ハズしても倒産しない。新規事業を辞めても既存売上がある、という保険があるだけで精神的余裕ができる。
- 投資家との相性は選べるユニコーン級を求められる大手VCは相性悪いかもしれませんが、比較的小さいファンドや事業会社CVC、エンジェル投資家は好意的に見てくれる場合がある。もともと黒字基盤があることを評価し、「確実に伸ばせそうな時」に追加投資を受け、上場を目指すことも可能。
- 売りやすい(M&Aしやすい)M&A先の企業にとって、すでに黒字基盤があるソリッドベンチャーは「赤字スタートアップ」より買いやすい。結果、小規模でもスパっと売却して起業家が次の会社を作る、という動きにもつながりやすい。
一方で、ソリッドベンチャーはJカーブスタートアップのように100倍・200倍を狙う“爆発力”に欠けると言われがちです。しかし、そこは経営者次第で、PL脳を切り替えて大胆に攻めれば急成長も十分狙えますし、逆に自社だけで成長を続ける堅実路線を維持してもよいでしょう。
いずれにせよ、創業直後から安定収益を作れるビジネスモデルを選ぶ利点は大きく、これから起業を考える人にも有力な選択肢となっていくはずです。
造語、ソリッドベンチャーについて個人的意見をまとめました!ビジネスモデル・事業についてラフな面談受け付けてます!
FAQ
Q. スタートアップとの違いは?
A. 赤字前提のJカーブ型ではなく、黒字を維持しながら探索を続ける進め方です。
Q. 既存ビジネスがないと始められない?
A. 小さな受託やコンサルで キャッシュエンジン を作る方法が現実的です。
Q. 大きな成長は狙えない?
A. PLコントロールを前提に“攻めモード”へ切り替えれば急成長も狙えます。
まとめ
ソリッドベンチャーとは、黒字基盤と新規探索のサイクルを止めずに回し続ける企業状態の構造です。赤字を掘らなくても挑戦できるますし、むしろ黒字基盤こそがこれからの時代、挑戦を持続させる最大の武器になると思っています。